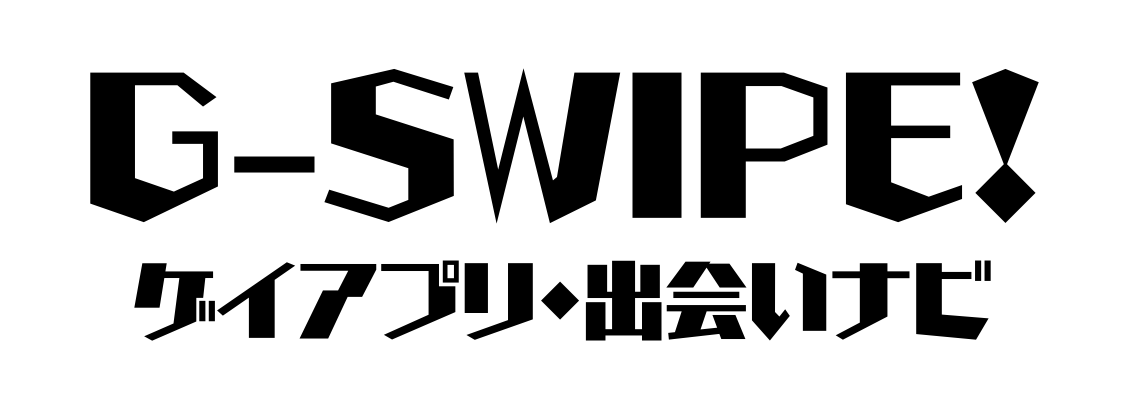想いを告げられずに終わる恋は多い。
この世の8割の恋は、そんな片想いであると僕は思っている。「この人ちょっと良いな」という淡い気持ちから「この人に愛されなくちゃ生きている意味がない」との熱烈なものまで。
そして片想いは楽しい。付き合う前のあのドキドキ感や、好きな人がこの世界に存在する喜びには何物にも代え難い。
憧れの東京で恋をしよう
これは僕が大学生になったばかりの頃の話だ。
僕は東京に憧れを抱きつつ、進学を機に上京してきた。
出会いも無ェ、彼氏も無ェ、若い男も歩いて無ェ、パッとしない田舎での青春を僕は東京で取り戻す気でいた。
山手線に内回りと外回りがあることすら知らないくせに、スマホにはAMBIRDがきちんとインストールされている用意周到ぶり。
知らない人とネット上で知り合い、リアルに会うという行為もすぐに慣れた。コミュニケーションが苦手ではなかったので、我ながら器用にやっていると思いながら2,3人と会ってきたが何か違う。
誰に対しても心が動かされないのだ。
恋の予感はもちろん、彼らと友達として仲良くしたいかと聞かれれば答えはNO。(本当すみません)
僕はここで、初めてオンラインで友達や恋人を作ることの難しさを知った。
しかしそう簡単には諦めない。軽く絶望を感じつつも根気強くアプリを続ける。
まずは学業に専念しろよと言いたくなるところだが、大学1年の夏頃に僕はある男性と知り合う。
思ったもの勝ち「運命の出会い」
彼の名前は亮輔くん(仮名)。僕より2つ年上の彼は、メッセージからも伝わる穏やかな雰囲気の人だった。共通の趣味や好きな映画の話で盛り上がった僕たちは、とんとん拍子に事が進み、気づけば都心の小洒落たカフェでアイスティーを啜っていた。
「亮輔さんは、よくこういうおしゃれなカフェに来るんですか?」
「うん、よく来るよ。落ち着いた雰囲気の店だから、じっくり話をしたい時とかにね」
この人は僕とじっくり話をしたがっている…。ドキリと胸が鳴った後に、行きつけのオシャレなカフェがある彼のスマートさに感心した。
この人は僕が今まで会ってきた人達とは明らかに違う。彼とだったら何時間でも一緒にいられる気がした。アイスティーだって一生啜れる。
また、会話が進むうちに互いに同じ大学に通っていることが判明し単純だった僕はすぐに運命を感じて身震いした。
「えー!まさか同じキャンパスに通ってたなんて!どこかですれ違ってたかもしれないですね」
「そうだね!でも君とすれ違ったりしたら覚えていると思うんだけどな(笑)」
「えっ…」
「だってうちの大学で金髪は珍しいもん(笑)」
「あ…あぁ(笑) (タイプだからと違うんかい)」
そうなのだ。僕は大学デビューとして自らブリーチ剤を頭にぶっかけて、下品なタイプの金髪に染め上げていたのだ。亮輔くんと出会った頃も、僕の頭はキンキンに輝いていた。今考えるとゾッとせざるを得ない。
亮輔くんのドキッとする甘い発言に心臓を撃ち抜かれた後に現実に引き戻された僕だが、ここで彼への好意を確信することになる。
今回が初対面なのに、こんな気持ちになるなんて…。
これが亮輔くんとのファーストコンタクトだった。
その後も、彼とは同じキャンパスに通っているので頻繁に会っていた。大学の学食でお互いの学部のことを話したり、近くのラーメン屋で激辛ラーメンを食べて僕が窒息しそうになり2人で笑い合ったりもした。僕が1年生で亮輔くんは3年生。学食の美味しいメニューから駅から大学までの最短ルートなど、本当に色々なことを教えてくれた。
その時に授業で学んだことは1ミリも覚えていないのに(おい)、彼の発言は今でもその時の風景と共にしっかりと思い出せる。
これを恋と言わずして何を恋と言うのだろうか。僕は完全に亮輔くんに片想いしていた。
亮輔くんは僕のことをどう思っているんだろう。
ゲイアプリを通じて知り合った仲とは言え、彼の気持ちを確かめられずにいた僕は悩んでいた。
彼の決断
出会ってから数ヶ月が経って冬になる。
彼は就職に向けて準備をしていて忙しそうだった。一方僕は、風水にハマって玄関や水回りを磨き上げることに精を出していた。困った時の神頼みではないが、亮輔くんに振り向いてほしくて恋愛運を上げるというトリッキーなアプローチをとっていたのだ。
その日も授業が終わり、2人並んで大学の前を歩いていた。
「亮輔くんも大変だね。就活はこれからが本番だし」
「まあね…」
「辛くなったらいつでも言ってね。飛んでくから(笑)」
「うん」
「………」
いやに沈黙が続く。彼の返事も明らかにそっけない。何か変なことを言ってしまったのだろうか。それとも体調でも悪いのだろうか。不安になって彼の横顔をじっと見ると、何やら思い詰めているようだった。思い詰めている横顔もいいなァ…と思う僕に、一つの予感が浮かんだ。
もしかして告白しようとしてる…?
出会って数ヶ月、かなり親しくなった僕たちの関係は今、ようやく友達から恋人にステップアップするのかもしれない。そう思うと一気に心臓の鼓動が速くなった。道端で告白されるのも、さりげない感じがして良いかもなあ…。よし、どんとこい。などと1人悶々と考える僕に、彼は口を開いた。
「実は俺、就活はしないんだ。イギリスに留学することに決めたんだ」
「へ〜イギリスね。…え?イギリス?」
「うん。向こうの大学に編入する形で」
「え?どれくらい?期間は?」
「3、4年はいるつもり。実はもう来月に日本を発つんだよね」
「らいげ…」
「君にはもっと早く言うべきだったのに、なかなか切り出せなくて…。ごめん」
「いや…大丈夫。あの、留学すごいね…」
ここから先の会話の記憶はない。きっとその時、僕の体は自動運転に切り替わり亮輔くんの話の相槌を適当にうち、フラフラと歩くので精一杯だったのだと思う。悲しさよりもショックが大きくて、動揺を悟られないように振る舞った。
駅のホームで彼と別れた後に、ふと、恋愛運を上げるために風水の本を読みながら玄関を本気で磨いていた自分が憎らしくて可哀想になる。ようやく涙がジンワリと滲み出てきた。
僕の片想いが片想いのまま散った瞬間である。
それから亮輔くんは予告通り1ヶ月後に、イギリスに旅立った。
東京に憧れを抱いて上京した僕のように、彼はイギリスに憧れを抱いていた。ただそれだけのことだったのだ。
今思うと、どうして受け身のままだったのだろうと後悔の念が湧く。風水で運気を上げて彼に告らせようなどと言う考えは受け身の骨頂だ。おまけにトリッキーすぎる。
彼に好意を抱いた時に告白していたら付き合えただろうか。
彼と仲良く遊んだ時に告白していたら付き合えただろうか。
どう足掻いても後の祭りである。
しかし僕は気付けた。恋愛は待ってばかりいたらチャンスを逃すのだと。
そして、どんな恋も最初は誰かの片想いから始まるということも。