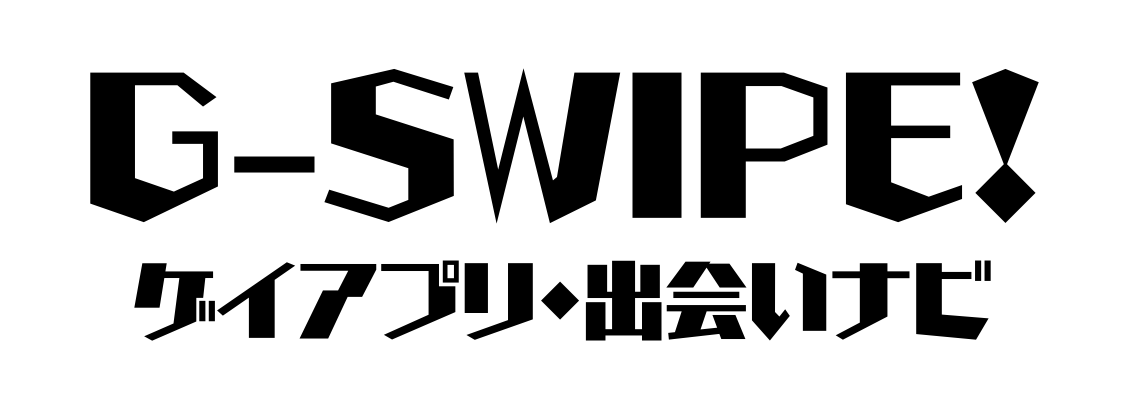Charaはタイムマシンは来ないと歌い、ドラえもんはタイムマシンを駆使して冒険をする。
様々な創作作品で描かれるタイムマシンが実現すれば、人類の多くは恋愛絡みの目的で使用することになるだろうと思うのは、僕だけだろうか。
彼との出会いは1年前
約1年前、大学2年生だった僕は、アプリを通じて2歳年上の大学生と出会った。彼の名前は圭吾。僕とは違う大学に通う4年生だったが住んでいる場所が近かった。
距離が近いと食事やお茶に誘いやすく、よく2人で近所を歩き回って遊んでいた。2人とも散歩が好きだったから、色々なことを歩きながら話したものだ。
彼は理系で僕は文系。
僕は理系の人に、まともな人がいないというとんでもない偏見がある(良い意味でも良くない意味でも)。
そんな最低な偏見を裏切らず、彼ももれなく変人だった。生きることに独特なポリシーを持ち合わせて自分の哲学を持っていて、多少理解し難い言動をとることもあったが、僕はそんな彼を尊敬していたし淡い恋心を抱いていたように思う。
しかし出会って2ヶ月ほどで僕たちの交流は途絶えた。実にあっけなく終わってしまったのは彼が就活を始め、多忙になったからだと理解している。
僕が飽きられたとかじゃないことを願う…。
圭吾のことを思い出しては切なくなっていた僕も、彼のことをすっかり忘れて大学生活を謳歌した。時間は待ってくれないのだ。
そして1年が経った。
友達と喫茶店に行った時に、なんとな〜く胸がキュッとすることに気づく。運ばれてきたナポリタンを食べて思い出したのは他ならない圭吾だった。
そう、彼と数回その店に訪れていたのだ。口をケチャップで汚し、久しぶりにセンチメンタルな気分に陥った僕は、彼と付き合っていたわけでもないのに、頬杖をつきながら「あいつ、今どうしてるのかな」等と元カレぶった発言をして酔いしれた。
いても立ってもいられなくなり、試しに「お久しぶりです!あれから元気にしてますか」とメッセージを送ると1日たって返事が来た。
「お久しぶりです。元気ですよ!そちらはどうですか?」
至極真っ当な返事は、丁寧で真面目な彼のパーソナリティを思い出させる。話は進み、僕は彼の行きつけの洋食屋に連れて行ってもらうことになった。
余談だが、誘いの返事で具体的に日付を決めにかかる人ってありがたい。“意志”が感じられて普通にキュンとくる。僕はそういう押しに弱い。だから圭吾よ、どんどん押してくれ…。
再会はドラマ
さて、1年ぶりに会う圭吾は髪がちょっと短くなった以外ほとんど変わらなかった。ハンチング帽に角張った黒い鞄が懐かしい。僕は彼のファッションが好きだったことを思い出し、話し方や佇まいを見て当時の気持ちが徐々に蘇ってくる。
「1年ぶり、ですよね。前もこうやって圭吾さんとお茶しに行ったこととか、懐かしいです」
「そうですね、よく散歩しましたよね。線路沿いとか歩くの楽しかったなぁ…」
「熱中症の一歩手前までいったやつですよね(笑)死ぬかと思いましたよ」
洋食屋の席につき対面すると、圭吾はあまり目を合わせてくれない。それは緊張なのか、元々人と目を合わせるのが苦手なのかわからなかった。1年前もこんな感じだったっけ…?
一抹の不安を抱えながらも僕たちは食事を楽しんだ。彼は就職せず、大学で研究を続けていることを知りなんだか嬉しかった。彼は彼のやりたいことをやっていると思うと不思議と安心できるのは、やっぱり彼のことが好きだったからだろう。そして今も…。
夏の始まり、恋の始まり
洋食屋を後にした僕たちは、コンビニでアイスを買って夜道を並んで散歩することにした。6月の夜は暑すぎなくて、歩くと心地よい温度の風に包まれる。僕はソフトクリーム、彼はチョコバーを片手に静かな住宅街をテクテク歩いていた。
適度な闇が効いているのだろうか。洋食屋にいたときよりも彼が饒舌になっている。1年という空白を埋めるかのように、僕たちはお互いに様々なことを尋ね合った。相手のボーダーラインを乗り越えないように探りながら、少しずつ。
その中で彼がどんな本を読むのかと僕に聞いた。
「最近読んだ本?えっとね、エッセイばっかりなんですけど…」
「あ、さくらももこのエッセイが好きって言ってましたよね。それを聞いて僕も読んだんですよ。面白かった」
「えっ」
思わずチョコを唇の端につけた彼を見上げると、くっきりとした横顔のシルエットが心に焼き付く。
僕はさくらももこの話をした記憶をすっかり忘れていたのに、彼は覚えていてくれた。それも1週間前とかの話じゃなくて1年前の何気ない会話を。この人の記憶の中に僕は生きていたのだ。
もうこの人を離したくない。理屈抜きで僕の頭がそう考えた。脈拍がアクセルを踏んだかのように急発進して背中に汗がジンワリと滲み出る。
「あ、あの…一年前、こんな風に散歩してた時、僕は圭吾さんのことが好きで、ドキドキしてました…」
口の中がカラカラになるのは背中の汗に水分が持ってかれたからだろうか。手も声も震える中、必死になって舌を動かす。
「そして…今日会って、やっぱりいいなって思います…」
これは告白になっているのだろうか。ただの意見表明ではないか。沸騰寸前の頭をフル回転させる僕は、そんなことは気にも留めずにただただ話し続けた。
「僕もです…。僕も、君のことがずっと好きでした。一緒にお茶したり、散歩するのが楽しくて…」
やっぱ好きだったんじゃ〜ん!嬉しい〜!!!と思ったのも束の間、ここまで聞いて僕は、しまった!!と我に帰った。どうしてこんなに衝動的に口走ってしまったのだろう。きちんと彼に恋人が存在しないかどうか、現在恋愛する意思を持ち合わせているかどうかチェックするべきだった…。
思い返せば僕の人生は大体このような衝動で突っ走り、壁にぶち当たることが常だった。今年の目標は「石橋を叩いて渡る」と元旦に餅を食いながら家族の前で宣言したではないか…。
血の気が引いていく僕に彼は続ける。
「今でも変わらず好きですよ。久しぶりに会って当時の気持ちをそのまま思い出しました(笑)」
「えっ…」
「また会ってくれますか。今度こそちゃんと付き合いたい」
自動販売機の逆光で彼の表情がよく確認できなかったのが悔やまれるが、恐らく相当緊張していたと思う。僕と同じくらい声が震えていたから。
僕は何回も首を縦に振り、恋に不慣れなカップルはこうして再び歩み寄ることになったのである。
胸のときめきが収まらぬうちに別れた後、夏の星空が広がる下でひとり歩く僕は1年越しの恋の予感を確かに感じていた。
タイムマシンはまだ、開発されなくてもいいと思った。