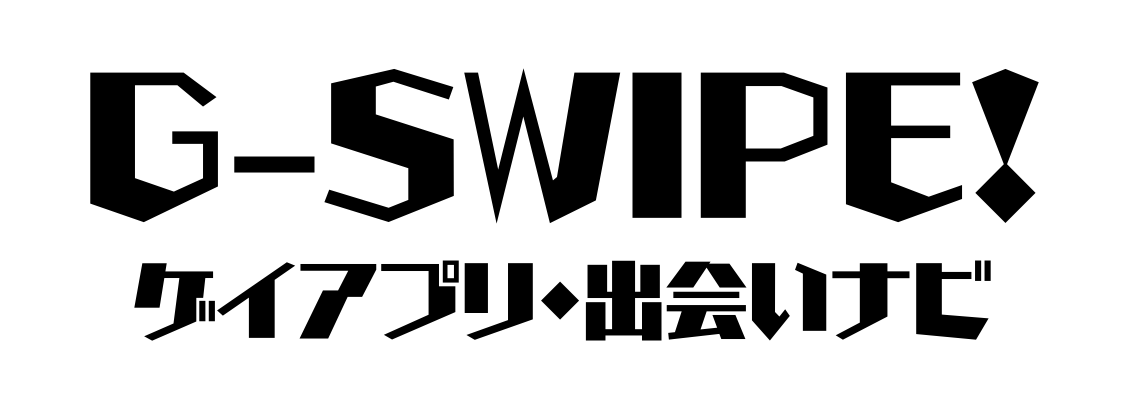この世の8割は片想い
想いを告げられずに終わる恋は多い。
というかこの世の恋の8割は片想いであると僕は思っている。「この人ちょっと良いな」などという淡い気持ちから「この人に愛されなくちゃ生きている意味がない」との熱烈なものまで。
そして片想いは楽しい。そりゃあ意中の人と恋仲になれればそれに越した事はないが、付き合う前のあのドキドキ感や好きな人がこの世界に存在する喜びには何物にも代え難い。
僕は誰にも打ち明けられない恋を、中学生の時にしていた。初恋だった。
中学生の初恋
地元の中学校に通う僕は、その時14歳だった。アダルトチルドレン、大人と子供の狭間、様々な名称をつけられる多感で青臭い思春期に、僕はテニス部に所属していた。
僕の通う学校は、必ずいずれかの部活動に所属しなくてはならない田舎特有の意味不明な掟が存在するため消去法で選んだのだ。他の運動部に比べて楽そうだと踏んで入部した僕の思惑は盛大に裏切られ、中学3年間、ほとんどの時間と労力をテニスに捧げることになる。
今の自分だったら速攻辞めているであろう厳しい練習にも耐えられたのは、恋をしていたからだ。それも同級生などという芋くさいガキにではなくテニス部の顧問の先生に、だ。彼の名前を仮に吉沢先生としよう。
吉沢先生は田舎の公立中学校にしては一際若く、大変爽やかな教師だった。担当科目は理科。理系科目が苦手な僕は中学3年間、つきっきりで彼に教えを請うことになる。
さて、部活だけでなく中学1年次から僕の学年を担当する吉沢先生に対して恋心を自覚したのは中学2年の時だったと記憶している。
運動神経のよろしくない僕は部活中によく怪我をしていた。どうしたらテニスでそのような怪我をするのか、周囲の人間から散々不思議がられてきたほどである。そんなのこっちが聞きたい。
そして、その日も僕は怪我をした。ボールを受けようとして足首を捻ったのだ。
…痛い。
激しい痛みを抱えてコート上でうずくまる僕に真っ先に駆け寄ったのが吉沢先生だった。怒られると思いきや、すぐさま僕を背負い込んで保健室へと運んでくれたのだ。
「大丈夫か?かなり痛いんじゃないか?」
「あ、はい…、かなり痛いです。すみません…(痛いに決まってんだろ)」
「お前よく怪我するからな(笑)気をつけろよー。でもそれだけ頑張ってるってことだから気にすんな」
この瞬間、僕は先生の温かい背中にしがみついていた。先生の大きな背中から薄いシャツ越しに体温、声の震え、息遣いなどがダイレクトに伝わってくるのだ。もはやその状況はセックスに等しい。こうして僕は完全に恋に落ちた。もう、足の痛みなど少しも感じていなかった。恋は市販の鎮痛剤をも凌ぐ力があることも、僕は初めて知る。
好意を自覚する前、吉沢先生はただかっこいい人という認識だった。背が高くてスタイリッシュだし、何より声が良かった。
体の芯が震えるような低い声で、リトマス紙の使用方法などを説明するのだ。いやらしい。
『保健室おぶさり事変』が起こってから、僕は彼の授業が楽しみでしょうがなかった。
あぁ、どこかに彼の気持ちを確認する恋のリトマス紙はないだろうかと薬品臭い理科室で何度思ったことだろう。授業が終われば意識は放課後の部活に向かう。テニスコートで先生にまた会える…!
このように、僕の中学校生活は吉沢先生がいてくれたおかげで1日1日が光り輝いていた。
僕だけが知る彼の優しさ
吉沢先生はかっこいいけれど、厳しい面も持ち合わせていたため生徒からの人気は中の下と言ったところだ。僕はそれが嬉しかった。皆が知らない彼の優しさを僕だけの秘密にしたかったからだ。
その優しさは時折、部活動の中で垣間見ることができた。僕が練習試合でコテンパンに敗北した時のことだ。前述の通り僕は運動神経が良くないため試合で勝つことは滅多にないのだが(それでもよく続けていたと自分でも思う)その日、あまりにも成長しない僕に苛立った吉田先生が僕をベンチに呼び出し強く叱責した。
今思うと大したことないと思えるのだが、当時はやはりショックだった。僕の心を支配したのは恥ずかしさや不甲斐なさではなく先生に嫌われたらどうしよう、という気持ちだった。大好きな人に怒鳴られるほど悲しいことはない。
今だったらそれも一種のご褒美と思えるかもしれないが、ピュアだった僕は気持ちをどう処理していいかわからず、ただ目に涙を溜めるしかなかった。
練習試合が終わり、皆が家路に着くときに僕は先生に再び呼び出された。
「ちょっといいか」
「はい…!」
「さっきは皆の前で怒鳴ったりしてごめんな。ちょっと感情的になりすぎてた」
追加の叱責を予感していた僕にとって、先生の謝罪はまさに晴天の霹靂だった。
「いや、そんなことないです。僕こそすみませんでした」
「これからは気をつけるから、お前も練習頑張れよー」
どうして人は厳しくされた後の優しさに弱いのか。その優しさが際立って感じられるからだろうか。恋する乙女のフィルターを装着していた僕の目から見れば、彼の優しさは僕への好意と同じに見えた。いずれにせよ、僕はますます彼にのめり込んでいく。
理科の実験中、吉沢先生が近づけば気が動転してガスバーナーの調節を誤り火柱を上げ、部活中に先生がコートに入って来れば持ってるラケットを落としていた。嘘のような本当の話である。初恋にして強烈な片想いを抱えていた僕だったが、もちろんこの想いは誰にも打ち明けられなかった。
同性で、教師と生徒なのだ。果てしなく高いハードルが2つもあることに軽い絶望を感じていた僕は、それでも情熱を燃やしつつ天文学的可能性を信じて生きていた。数万分の1くらいの確率でどうにかなってしまうのではないかと。(なるわけがない)
しかし、そんな淡くも図々しい望みはある日突然崩壊することとなる。
学年集会で恋は散りけり
週に1度の学年集会でそれは起こった。
多くの生徒がひしめき合う中、教師のクソどうでもいい話が響き渡る。吉沢先生は別だ。彼の話は一語とも聞き逃したくない…。彼が前に立って話を始める。
さわりの挨拶を終えたところで彼はニヤニヤしながらこう切り出した。
「えー、それとですね。この度結婚することになりました。この学年の皆さんには早く知らせたいと思っていたので、お話しします」
一瞬にして空気が変わった。女子の黄色い歓声や男子の感嘆する声、皆が顔を見合わせながら自然と笑顔になっていく。僕は別だ。その時の顔は、おそらく人生で最も血色が悪かったと思う。話は続く。
「相手は大学時代の同級生で、会社員の人です。婚約を機に同棲を始めました(笑)式はこれからなので、また追って報告したいと思います」
(割れんばかりの拍手)
追って報告しなくて良い。殺す気か。
吉沢先生は、その後も学年主任の先生に質問されて婚約者との馴れ初め等を披露していた。ちなみに婚約を決意したのは、打ち上げ花火を一緒に見た際に花火よりも彼女に見惚れている自分に気づいたからだと言う。やかましいわ。
でも、これほど幸せそうな先生を僕は今まで見たことがなかった。好きな人がいて、日々幸せを感じている先生の姿は僕自身と重なる気がした。唯一にして最大の違いは、それが片想いか否かであるかだ。
そんなことを思いながら僕はその晩、家の湯船に浸かりながら静かに泣いた。
同性で教師と生徒の関係に加えて妻帯者ともなれば、涙の一つでも落としたくなるだろう。別に本気でどうにかなると思っていたわけではない。それなのに、これほど絶望する自分に当時の僕でさえ驚いた。
これが生まれて初めて「恋」を知った一連の経験である。
左に女、右に男
数ヶ月後、学校の廊下の掲示板に結婚式での吉沢先生と配偶者の写真が飾られた。僕はそれを直視できなくていつも掲示板の前を足早に通り過ぎていた。しかし次第に好奇心が悲しみを上回る様になった頃、意を決して見ることにしたのだ。
一体先生はどんな人と結婚したのだろう。
誰もいない西日のさす廊下で息を呑んで掲示板の前に立つ。
写真には、はち切れんばかりの笑顔を浮かべる吉沢先生と健康的で優しそうな女性が映っていた。
悲しくて彼女の粗を必死になって探していたが、そんなことをしても写真の中の2人には指一本触れることはできないことに気づく。
僕の片想いは最後まで片想いだった。
2人の姿が涙で歪む。
下校時刻のチャイムが鳴った。