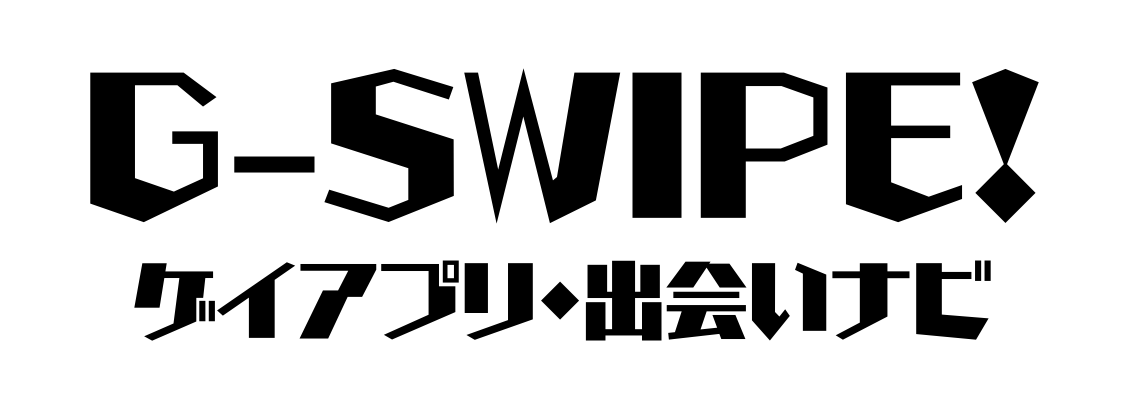学校、職場、地域など多くの場所でコミュニティは生じる。
多くの場合は、同じ価値観や似通った思考を持つ人たちが集まるが、時々自分に合っていないコミュニティに属してしまい苦労する人を見る。
あなたは、そのような経験はないだろうか。
僕はある。
本当の自分を偽り、身の丈に合わない自分像を作り上げていた。この話は、そんな愚かな僕が大切なことに気づくまでを描いた記録である。
コミュニティで繋がりたい
大学生になりゲイアプリを使うようになった僕は、それまで失っていた青春を取り戻すように色々な人と出会ってきた。
アプリで知り合った人と何回かデートをしても、仲良くなりきれずに次の出会いに進む。そんな決められたルーティーンをひたすら繰り返していると、ふと虚しくなる瞬間があるのだ。
駆け引きを感じさせる会話は確かに楽しい。しかし、それは一瞬で終わる。
実のある話ができなければ関係は続かず、後には何も残らない。
このままではいけないと思った僕は、趣味で繋がれると謳うAMBIRDというアプリを見つけてインストールした。
これだったら自分にも恋人ができるかも…。ゲイの友達だっていっぱい作れる…。
AMBIRDでは、その触れ込み通り様々なコミュニティが存在しユーザーはオンライン上でそれぞれのコミュニティに属すことができる。
趣味や考え方、自分自身のパーソナリティによってコミュニティを自由に選べる仕様になっているのだ。
アプリで自分の気になるコミュニティをピックアップし続けて数週間が経った。
僕の予想では、すでに同年代の友達がいくつかできていて、恋人候補も得ているはずだった。
はずだったのだが、どうしてだろう。恋人候補どころか同年代の友人さえできずに時だけが過ぎる現状に1人で静かに絶望していた。
おっさんみたいと言われても
しかし理由は薄々気づいている。
僕の趣味があまりにコアなのだ。
ここで僕が興味を持ってフォローしたコミュニティをご紹介しよう。
・地図
・園芸
・短歌
・散歩
・鉄道
・古本屋巡り
・昭和歌謡
いかがだろうか。
巷で雑誌を開けばモテる趣味、モテる遊びなどと銘打って様々なコミュニティが紹介されている昨今、これほどまでに「モテ」を度外視した趣味の羅列は珍しい。
僕の趣味を友人は口を揃えて、「おっさんみたい」と言う。(大変失礼)
しかし僕と同様の趣味を持つ同年代の人はそういないため、反論もできない。
ここはひとまず「モテ」までいかなくても、若い人が多くいそうなコミュニティを見繕わなくては…。期待と若干の焦りが入り混じる中、僕は今ドキのおしゃれな若者が好みそうな邦ロックのコミュニティに属することにした。
(僕は今ドキの若者は邦ロックが好きだという偏見を抱いている)
正直邦ロックなんて今でもよくわかっていない。僕はこの時、イケてる人と仲良くなりたいがために背伸びをしたのだ。
恐るべし、邦ロック
そんな不純な理由で邦ロック好きの人と繋がった僕だったが、割とすぐに同世代の人と仲良くなれた。
恐るべし、邦ロック…。
邦ロック好きの彼の名は邦夫にしよう。
邦夫は僕より3つ年上の社会人だ。流行りを追ったファッション、若者が注目すトレンドを先取りする彼は僕が想像する通りの今ドキの人だった。
かっこいい…。
そう、一言で表すと彼はイケていた。何故僕と仲良くしてくれていたのか疑問に思うほどだ。都会的で洗練された彼の趣味も嗜好も僕の目にはどれも新鮮だった。
会うたびに、僕は彼を質問攻めにするのが常だった。少しでも彼の要素を取り入れたかったからなのだと思う。
「邦夫くんの周りの友達も似た趣味の人が多いの?」
「え、まあそうだね。音楽の話題で仲良くなることが多いし」
「なるほどね…。やっぱり共通の話題がない人とは話しづらいもんな〜」
「まあ、同じコミュニティの人となら話しやすいよね」
同じコミュニティ…。僕の身体がズンと重くなる。僕が地図マニアで一日中地図を眺めていることを彼が知ったらなんて思うのだろう。
「邦夫くんの趣味とかかっこいいし、イケてる人たちと繋がれそう」
独り言のようにぽつりと呟いたのを、彼は聞き逃さなかった。
「俺は、ただ好きだからやってるだけだよ。趣味も遊びも、仕事もね。そこでできる繋がりは確かに大切だけど、自分の気持ちを優先させなきゃ」
邦夫くんの真っ直ぐで透き通った目は、僕の邪な考えを見抜いているようだった。人からどう思われるかを意識してばかりいた自分が恥ずかしくなる。
「そうだよね…!なんか勘違いしてたかも…ごめん」
「あと、邦ロック大して好きじゃないでしょ(笑)いつになったらハマるかと思ってたんだけどな(笑)」
それを聞いて僕は耳まで真っ赤になった。バレてる…!
僕のとってつけたような邦ロックの知識を目の当たりにすれば、そりゃ気づくと思うが予想だにしなかった彼の発言に心臓を鷲掴みにされた。
「君が一番楽しめることをやればいいんじゃないかな」
「…ありがとう。自分は邦ロックじゃなくて、邦ロックを聴く人が好きだったのかも(笑)」
それを聞いてにっこり笑う彼に、僕はどれだけ救われたことか。
背中を押されて見る景色
邦夫くんは僕の背中を押してくれたのだ。誰かの価値観や意見に沿ったコミュニティ選びではなく、素直に魅力を感じる所へ行けば良いと諭してくれた彼は、やはりカッコよかった。
今思うと僕はコミュニティ自体に恋していたんだな、と思う。
好きなことをやりながら様々な人と繋がることを決めた僕は、もう迷わない。
手始めにコアな趣味のサークルでも作るつもりだ。