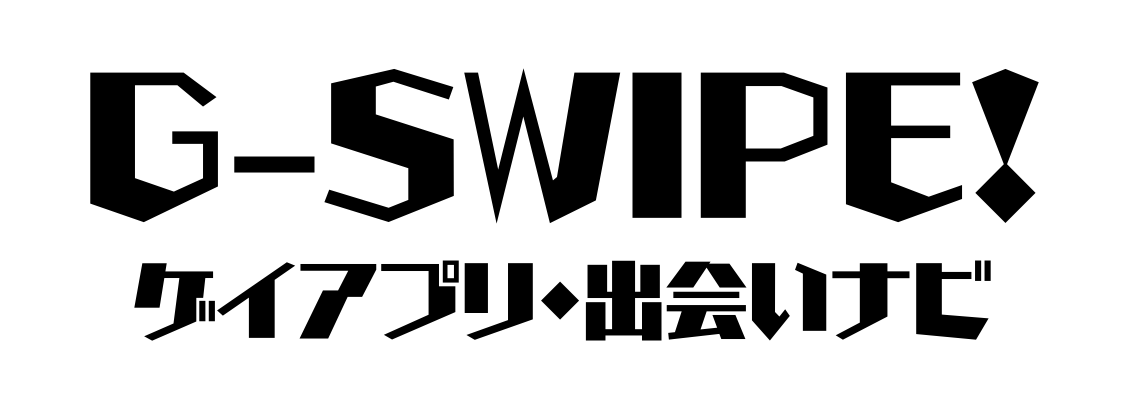半年後の運命
人は一生のうち何人と出会うんだろう。その中から一体、何人に運命を感じるんだろう。
記録的な熱帯夜がどこまでも広がる東京郊外のマンションのベランダで、僕は彼の横顔を見て考えていた。
右手にはタバコ、左手には缶酎ハイの組み合わせも、遠い向こうが都心だと夜景に照らされる雲でわかるこの光景も、きっとこれが最初で最後だ。
僕の隣に座る彼は、半年後に結婚することが決まっていた。
マッチング後のセオリー
___ピロン
大学の課題に追われていた真夜中に、誰かとマッチングしたことを知らせるアプリの通知が入る。
久しぶりに聞く通知音に遠慮がちに胸を弾ませる僕は、作業の手を止めスマホに手を伸ばす。
相手は、そう離れていない距離の26歳の人で見た目も悪くなかった。
ちなみに僕に好きな人のタイプはない。強いていうなら、落ち着いてて骨格がしっかりしている人だ。
そう、彼も健康的な骨に逞しい肉体をまとった好青年だった。
「初めまして!よかったら話しませんか」
「こんばんは。メッセージありがとう。よろしくお願いします」
彼はもう忘れているだろうが、僕たちの最初のやりとりはこんな感じだ。アプリでのファーストコンタクトなんて皆、同じようなものだが普段自分からメッセージを送らない僕からアプローチしたので印象に残っている。
相当気になっていたのだろう。
郊外で一人暮らしをする彼から、医療系の仕事をしていることやバイセクシャルであること、実家でパグを飼っていることなど様々な情報をメッセージを通じて仕入れていった。
これもセオリー通り。マッチングした後の一連のプロセスを僕は淡々とこなしていく。彼とのメッセージは楽しくて少なからずときめいているはずなのに、どこか冷静な自分がいることに気づいて戸惑ったりもする。
おそらく期待することを避けていたのだと思う。しかし、会ったことのない彼に思いを馳せる中、その日はやってきた。
熱帯夜と脱力
「よかったらこれから会わない?」
彼からの提案だった。時刻は20時を過ぎ、昼の暑さを引きずるムッとした夜だった。俺の家に来いという趣旨のメッセージ読んで、複雑な気持ちになる。嬉しくないわけではない。ただ彼の家に行ったらもうそこまでで、それ以上の関係の発展は望めない。
しばらく考えた末、彼に会うことにした。
熱帯夜がそうさせたのだと今になって思う。片道30分の夜道で自転車をかっ飛ばし、息を切らしながらaikoの「キラキラ」を熱唱したのも、彼にとって都合の良い男に成り下がったのも全部あの夜が悪い。
彼のマンションに着いた。熱唱と緊張により口の中が乾いてしょうがない。ドキドキする僕を笑顔で迎え入れた彼は、実際に見てもかっこよかった。自転車を漕いで汗だくになったおでこを拭い、テレビを見ながらジュースを飲む。
「まさか本当に来てくれるとは思わなかった(笑)悪いね」
「どうせ暇だったからいいんです。夜道を自転車で走るの好きだし」
「ずっと会いたかったから来てくれてマジで嬉しい。ありがとう」
彼は良くない人だと、ちょっと話しただけでもすぐわかる。妙に慣れていて余裕のある言動は、男女問わず様々なシーンで活用してきたことが窺える。これまでのやりとりからも感じてはいたが、要するにチャラいのだ。
この甘いマスクと言葉に引っかかってきた虫たちはどれくらいいるんだろう…。
そして今夜、僕もその虫達の一員になるのかと思うと急に力が抜けてきた。
不意に彼がテレビを消して部屋に静寂が訪れる。飲んでいたジュースの炭酸の弾ける音がうるさいくらいだ。
そして僕は虫になった。
慣れないタバコと缶酎ハイ
メッセージのやりとりの時と同様にどこか冷静だったのは、何にも期待したくなかったからだろうか。それなりに楽しみながらも、僕は彼の行動と部屋を詳細に観察していた。部屋の間取りから家具の配置、そのセンスまでをチェックした後に彼の顔を見る。なるほどなあと思いながら内心楽しんでいた。(何がなるほどなのか)
我ながら不気味な奴である。彼も変な奴を招いてしまったものだ。
そんなこんなで再び静寂が訪れる。
「タバコ吸う?」
「え、じゃあ吸ってみようかな」
「お酒もあるよ」
僕は慣れないタバコと缶酎ハイを持ってベランダに出た。彼が無駄のない動作でタバコに火をつける。時刻は1時を過ぎていたと思う。暗闇の中に小さい二つの赤い光が浮かび上がり、頬に受ける夜風は生ぬるくてなんとも言えない。
「てか片道30分もかかったんだ。そんなに遠いとは思わなかったわ…」
「全然。前に片道3時間くらいかけて渋谷の方に行ったことあるし」
「チャリで!?すごいね(笑)」
彼なりに気を遣っていたのだろうか。それとも峠を越えて酒が入り、気が緩んだのか饒舌になっていた。
「俺ねー、ここからの景色がめっちゃ好きなんだよね」
「確かに綺麗だね、都心の方が明るくて面白い」
「でしょ!でも、もうすぐ引っ越すんだけどね。結婚するから」
「え、あ、結婚するんだ!」
昇っては消えるタバコの煙
どうしよう…。婚約者の部屋にノコノコやってきてしまったことを今更ながら後悔して缶酎ハイを傾ける。もうここに来ることも、彼に会うこともないと心の中で誓う。
期待なんか持つなよと言わんばかりに、彼が刺した釘はメキメキと効果を発揮していた。というか結婚するのに何をしているのだお前は…。声にならない思いが渦巻く。昇っては消えるタバコの煙がやけに切ない。
ここにきて冷静さを欠き、初めて動揺する僕の耳に彼の鼻歌が聞こえてきた。なかなかエモーショナルな雰囲気を演出するじゃないか、と思っていたら聞き馴染みのあるメロディであることに気づいた。
彼は僕がここに来るまでにチャリを漕ぎながら歌ったaikoのキラキラを、喉の奥で奏ていたのだ。
もはや心穏やかではいられない。僕の心拍数と血圧はアルコールの力も借りて一気に上昇した。
「えっ…その曲…」
「あ、わかった?aiko好きなんだよね」
「自分も、好きです…」
「同じだね」
まさか、「その歌を息を切らせて熱唱しながらここまできました〜」などと間抜けな説明などできるわけがない。そもそも言ったところで何かが変わるわけでもない。行き場のない感情と思いを酒で流し込む。彼の鼻歌は2番に差し掛かった。僕は目を閉じて彼の低く震える喉を想像していた。
翌朝、僕は朝日を浴びながら家路につく。見慣れた道に差し掛かれば、昨晩の出来事が夢か現実かよくわからなくなっていく。夢だとしたら結構綺麗な夢じゃないだろうか。
そんなことを思いながら僕はただ無言でペダルを漕ぎ続けていた。
日光を反射してあらゆる物がキラキラひかっている。
彼のその後は、知らない。